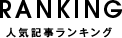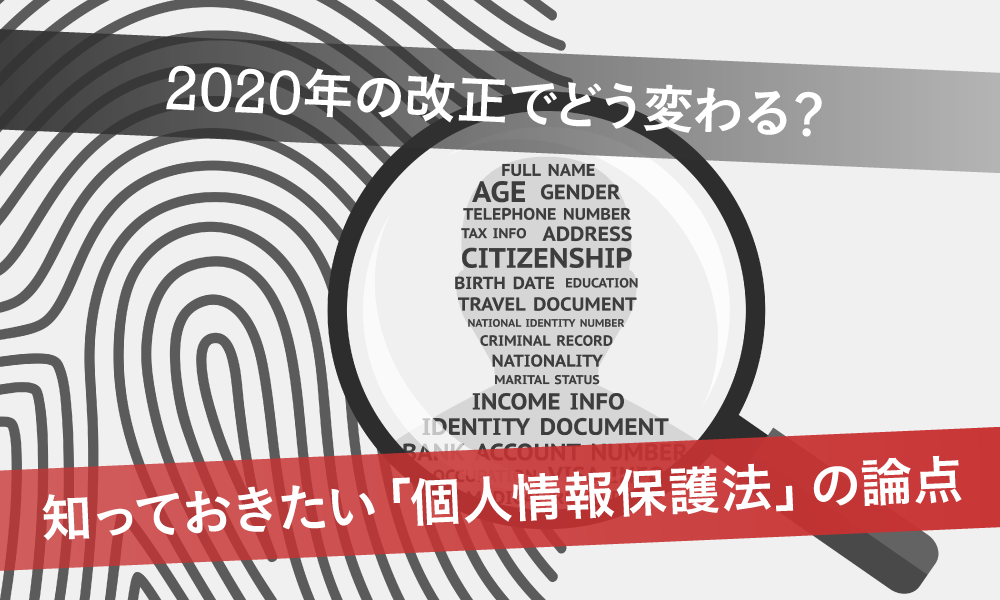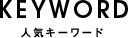リアルな世界から集めたデータが新たな価値を生み出し、あらゆる企業・産業・社会を変革していく一連の経済活動を「データ・ドリブン・エコノミー(データ駆動型経済)」と呼び、そうした時代に何をするべきかを説く、東京大学大学院工学系研究科教授の森川博之さん。彼が強調するのは、日本の強みである現場の気づきの重要性だ。
リアルデータの活用は現場の人間の気づきが必要
「私は従来インターネットで取れていたデータとIoTなどで取れる物のデータ、位置のデータなどを区別して考えています。前者はバーチャルでサイバー空間でのデータ、後者はリアルなデータ。このリアルなデータがIoTの活用や5Gのサービスインなどによって、どんどん集まり、活用が進む。それによって新しいビジネスや、社会の変革が起きると思っています」
21世紀の石油とも言われるデータは、マーケティングや流通分野での活用が目立っているが、森川氏はこれまで人出をかけていたようなアナログ的に行なっている分野こそ、変革の可能性があるという。
「例えば、国土交通省の地方整備局は国道で地すべりが起きないか、もし、危なかったら通行止めにする、といったことをパトロールして判断しているのです。地中にセンサーを仕込んでおいて、水分量などを測れば地すべりが起きるかどうかは、その現場に行かなくてもわかるようになり始めている。このように、いま人が行なっているようなこと、例えば河川の監視などもそうですが、こういうことがセンサーや無線通信などを使うことで、自動化したり、省力化することができる。
埼玉県にあるイーグルバスというバス会社の事例も興味深いです。ここでは、バスにGPSセンサーと乗降客数センサーを設置して、どのバスに何人乗って、何人降りたかというデータを集めたんです。そして、バス停の位置を再設定したり、時刻表を変更するなどして、改善を積み重ねていったら、赤字だった路線が黒字化したんです。地方のバス会社は、経営難が叫ばれていますが、ちょっとテクノロジーを活用すると、劇的に変わることがあるんです。そういう成功事例にもっと目を向けて欲しいと思っています」

森川氏は、東大教授の肩書で、全国各地の企業や商工会議所で講演することが少なくない。その際は『これから偉そうに、上から目線でお話をしますが、僕自身、何をやればいいかわかりません。それでも、みなさんの周りに、何かあるはずです。気づいていただくようにするのが、僕の役割です』と同じ目線に立って話をするという。
「現場の人に気づいてもらうことが大切です。これって、分析してみると何かおもしろい結果が出るんじゃないか、といったことが現場の人から自然と上ってくるようになるのが理想です。AIの導入が叫ばれていますが、結局はツールなんです。どんなツールかというと、人間が気づかないようなことも分類をしてくれるツール。
ただし、分析したら何か発見があるのではないか、何か分類できそうだ、という気づきは、AIには見つけられない。そこは、現場の人間が気づく必要がある。
あとは、想いです。これってデータを分析したり、活用すれば問題解決や発見があるはず、という絶対的な想い。それに根拠がなくても良いんです。ずっと、そうやって試していると、ある日、偶然に見つかることがあるし、テクノロジーが進化することで直感的に気づいたことが可視化されるということもありますから」
日本発の構想が生まれない理由は組織にある
気づきと想いを持つ現場。データ・ドリブン・エコノミー時代に対応していくためには、組織を変えていく必要があると森川氏は考える。
「まず、失敗を許容する組織になることが大事ですね。マネジメント層が、現場の失敗をある程度は許容しないと、新しいことに取り組みにくい。
あと、人事についても、ガーディアン型(守護者、保護者)と、スター型(突出した才能を持つタイプ)の2種類があると思っています。いまあるビジネスをきっちり遂行していくにはガーディアン型で、新規事業などはスター型。さらには、ガーディアン型には階層型の組織、スター型にはフラットな組織が向いている。このように、人のタイプ、担当させるビジネスの領域、それに向き合う組織という要素を、適切に組み合わせていく必要があります。この適材適所、リソース配分が上手く行っていないケースがある。ここは、考えていく必要があると思います」
森川氏は、日本は技術が優れていたので、良いものを作ればビジネスが上手くいった歴史が長く、そうしたマネジメントやリソース配分などときちんと向き合ってこなかったのでは、とも考える。新興国に追いつかれるのでは? ということに気を取られがちだが、ドイツが「インダストリー4.0」と呼ぶ第四次産業革命を仕掛けたり、GEがインダストリアル・インターネットを提唱するなど、本来日本が強いはずのモノづくりの分野で、次の一手につながるような未来像を描ききれていないことに警鐘を鳴らす。

「技術力では、ドイツと大差ないんです。大きく違うのは、ドイツはEUの経済圏で、フランスやイタリアなど違う文化圏の人たちと議論をしたり、一緒に仕事をする機会が増えました。それまでは自国内で行なってきたことを、(EU圏内とはいえ)外国の人々とコラボレーションする必要が出た。そこで、磨かれた経験は大きい。
日本人から見ると、実物や実体がないなかでの議論に意味があるのか、と思うのですが、実は、何もないところから枠組みを作ろうとすること自体に意味があるんです。仮に失敗をしても、その思考形態が経験値として残り、それが積み重なっていくと強みになっていくからです」
いま日本は、北東アジアの周辺諸国と摩擦が増え、安全保障上の懸念も高まっている。日本だけでなく、異なる文化を持つ外国の人々と対話的関係を強めることで、自らの技術を磨く必要がある。
森川氏が提唱するデータ・ドリブン・エコノミーをテイクオフさせるには、そうした視点も必要なのだろう。

森川博之氏
東京大学大学院工学系研究科教授。
1965年生まれ。1987年東京大学工学部電子工学科卒業。1992年同大学院博士課程修了。博士(工学)。2006年東京大学大学院工学系研究科教授。2007年東京大学先端科学技術研究センター教授。2017年4月より現職。IoT、M2M、ビッグデータ、センサーネットワーク、無線通信システム、情報社会デザインなどの研究に従事する。著書に『データ・ドリブン・エコノミー デジタルがすべての企業・産業・社会を変革する』(ダイヤモンド社、2019)。
取材・文/編集部 撮影/高橋宗正