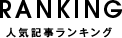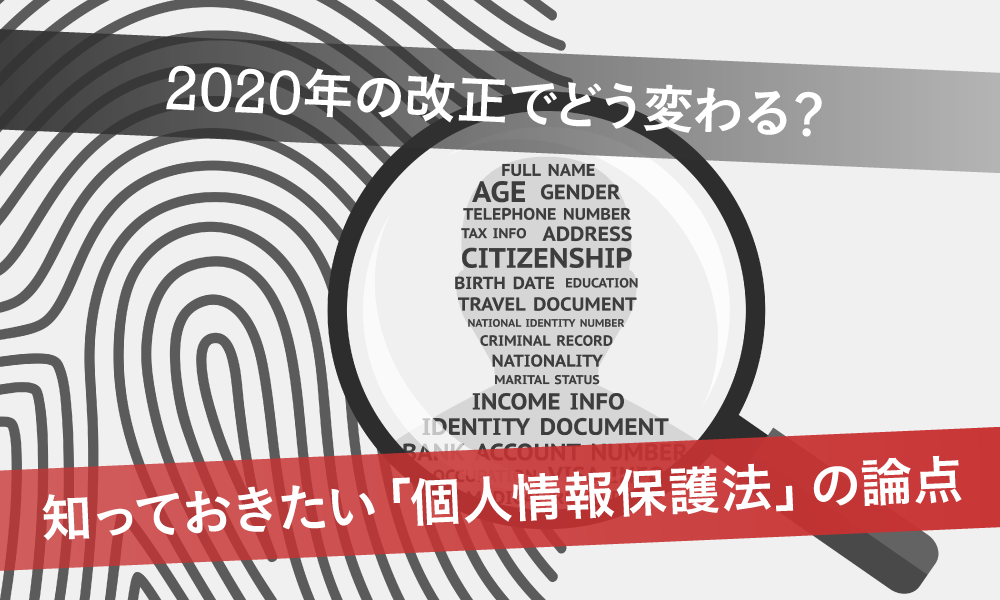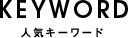お笑い芸人、『ピコ太郎』のプロデューサー…最近では経済番組での司会も担当するなど、活躍の幅をさらに広げる古坂大魔王氏。
弱肉強食の芸能界で「信用」を積み重ねてきた古坂氏は、独自の仕事哲学を持っているはず――そうした仮説のもと、同氏にお金の使い方や、信用の積み重ね方を訊きました。若手時代からほぼ全収入を衣装費にあて、音楽機材に700万円を投資した理由から、ピコ太郎のヒットの源流たる「畏怖」、そして「カバー」の重要性まで、ヒットの裏側に隠された戦略を明らかにします。
芸能界の超大物たちは全然尖っていなかった
――古坂さんが「お金」や「信用」をどう捉えているのか、お聞きしていきたいです。まず、これまでどのようなお金の使い方をされてきたのか、お話しいただけますか?

古坂大魔王氏
古坂:多くのお金を、お笑い芸人としての「信用」を得るために投資してきました。特に、衣装にかけるお金は惜しみませんでしたね。
――衣装が信用に結びつくのですか?
古坂:はい。デビュー当初、先輩から「なるべく好感を持たれるような衣装を着ろ」と言われたんです。当時は「ネタさえおもしろければ問題ないだろう」と、少なからず反感も覚えましたけどね。
しかし、お笑いの世界はひとネタ数分の世界。ネタに集中してもらい、数分の中で確実に笑いを取るために、観客から邪念を排除することが大切なんです。お客さんが服に違和感を覚えてネタに没入できない、といった事態を避けるためにも、しっかりとした衣装を身につける必要がある。
そう気づいてからは、衣装にとことん投資するようになりました。月数万円の収入だった若手時代でも、ほぼ全収入を衣装の購入費にあてていましたね。
――ネタに集中してもらうためにも、まずは衣装で信用を得るのですね。
古坂:もちろん衣装だけでなく、「教科書の“1ページの1行目”から、順番にきちんとやる」ことを心がけています。挨拶する、遅刻しない、後輩にあれ買って来いとか言わない、先輩風を吹かさない…そうした基本的なことを、当たり前にやり続けることで、人としての「信用」も積み重なっていくと思います。
――なぜそう思うようになったのでしょうか?
古坂:芸人として売れている「超一流」たちが、みんな「いい人」だったんですよね。僕自身、若いうちは尖ろうと必死だったんですが、彼らに会ったとき「あれ、全然尖ってない…」と気づいたんです。「やばい、俺はこれまで何をやってきたんだ」と思いました。改めて、「ちゃんとやる」ことの重要性に気づかされましたね。
劣等感をバネに、“攻めの投資”を続けてきた
――とはいえ、「ちゃんとやる」だけでは、厳しい芸能界で売れ続けることは難しい印象もあります。その他に、お金の使い方で意識されていたことはありますか?
古坂:自分だけのポジションを得るために、音楽機材にもかなりの額を使ってきました。20年前くらい、まだ収入も全然安定しない若手時代に、当時最先端のシンセサイザーやサンプラーなど、700万円分の音楽機材を購入したんですよね。芸人仲間や先輩からはバッシングされました。「そんなことをしている場合か」って。
――なぜそこまでのお金を?

古坂:芸能界には、年功序列的な側面もあります。その「順番」を飛ばすためには、隙間を狙うしかないと思ったんです。
当時は、とんねるずさんをはじめ、音楽活動も行なうお笑い芸人もいるにはいましたが、自分で音楽を作るお笑い芸人はいなかった。「ポジションを取るならここだ!」と思いましたね。今でこそ、舞台にサンプラーを持ち込みネタを披露する芸人も増えてきました。しかし、サンプラーは今でこそ1〜2万円で買えますが、当時は17〜8万円と、かなり値が張るものでした。だからこそ、そこに賭ける価値があった。安いサンプラーが出てしまった瞬間に、もう投資のタイミングとしては遅くなっているんですよね。
――他の誰も気づかないサンプラーに目を付けられたのは、ものすごい慧眼ですね。
古坂:根本には、劣等感があったのだと思います。僕は青森県で三兄弟の次男として生まれ、上京後は小さな個人事務所に所属していました。
幼少期は長男として大切にされる兄とかわいがられる弟に劣等感を抱き、上京後は生まれ育った青森と東京という街のギャップや大手事務所所属のタレントに引け目を感じていました。だからこそ、「こいつらにどうにかして勝たないと…」と死に物狂いで考えるようになったんです。
価値は「畏怖」から生まれる?
――現在のお話についても伺いたいです。古坂さんが、いま価値があると感じるものは何でしょう?
古坂:怖いもの、畏怖を感じるものです。
人はわけの分からないものや、新しいモノ・コトを知ると「びびる」じゃないですか。「びびる」という感情には、恐れが含まれますよね。ただし、その恐れというのは単純な恐怖ではなく、「なんかすごいぞ!」「なんでこんなこと思いつくんだろう…」といった畏怖に近いものだと思っています。
――畏怖を感じるものに、価値があると。
古坂:最近はみんなその「畏怖」に飛びついている感覚があるんですよね。たとえば、「堀江さん(堀江貴文氏)が●●と言った」「落合さん(落合陽一氏)が◯◯と言った」と追いかけている人たちも、最初に抱いた感情は、「なんなんだ、この人は…」「何を言っているんだ」といったわけのわからなさから来る「畏怖」だったと思うんです。
理解できないんですよ。だからこそ、もっと知りたくなるし、分析したくなる。そうして、その人が言っていることや書いたものに、価値が生じるんだと思いますね。
――たしかに、全く新しいものにふれたときの感情は「畏怖」に近いのかもしれませんね。「理解しがたい」ものだからこそ、知りたくなる。

古坂:実はピコ太郎もそこを意識して生み出されているんですよね。「どうやったら世間から理解されずにいられるか」を考え尽くしました。
1分で終わってしまう曲、全身アニマル柄の妙な衣装、「ペンパイナッポーアッポーペン」という謎の言葉。「ピコ太郎」というかわいらしい名前なのに、顔はかなりの強面。でも、しゃべりだすととても丁寧でやさしい…意味が分からないですよね(笑)。
――たしかに、冷静にわけが分からないですね(笑)
古坂:『PPAP』という曲も、「理解しがたさ」を意識してつくりました。常々「日本の音楽が海外の流行の後追いばかりで悔しい」と思っていたのもあり、「どこにもないトラックを作ってやろう」と。
そして、極端に音を少なくし、ファミコンのピコピコ音を使うことを決めました。僕はファミコンの音は「超かっこいい」と思っているんですよね。
単独ライブでピコ太郎を初めてステージに上げたとき、観客はまさに「なんだこれは…」というリアクションだったんです。笑うというよりは、ざわざわしていて。そうした観客の姿を見て、「もしかしたらバズらせれるのではないか?」と直感しました。まさか、あそこまでいくとは思っていませんでしたが(笑)。
ヒットの最短距離は「カバー」。権利は主張しつつ、どんどんパクらせよう
――ピコ太郎ブームの火付け役となったジャスティン・ビーバーのツイートで、引用されていたURLが実は複製された偽物だったという話も聞きます。利益が正しく表現者に還元されない、インターネットの状況をどのようにお考えでしょうか?

古坂:自分の作品がパクられても、「子供にネタを真似された」くらいに思っておけばいいのではないでしょうか。
たしかに、コピーが流通したことで損なわれた利益はあります。クリエイター側も、権利はしっかりと主張すべきです。だけど、気にしすぎなくていいと思います。いざという時は、専門家にお任せすればいい。
多くの人に知ってもらうために、一番早いのは「カバー」なんですよ。PPAPがあそこまで世界中に届いたのは、みんなが真似してくれたから。悪意を持ってコピーする人なんて、全体の1%程度だと思います。
――PPAPも、世界中でカバーされているだけでなく、アレンジ版の動画がインターネット上に溢れています。
古坂:これほど嬉しいことはないです。「出し手」としての僕のネタを、「受け手」がアレンジして発信してくれることは、「こういう感じもありですよね」という自己主張だと思うんです。「あ、なるほど。君はこれをバラードにしだんだ」「インド系にしたんだ」と、ファンレターのやりとりのようで、すごく楽しいんです。
もちろん、インターネットで表現することにはリスクも伴います。しかし、大きな可能性が秘められている。構造や仕組みをしっかりと理解した上で、自由に表現することを楽しみたいですね。

古坂大魔王氏
青森県出身、1973年生まれ。1990年代に「底ぬけAIR-LINE」として『ボキャブラ天国』に出演。2003年にはお笑い活動を休止し、「NO BOTTOM!」として音楽活動に専念。現在はピン芸人として活動しながら、2016年にはプロデュースするシンガーソングライター「ピコ太郎」が世界的に大ヒットした。新曲をYouTubeに10週連続アップした『PIKO 10PROJECT』公開中!https://bit.ly/2KGfbfa
取材・文/鷲尾諒太郎(モメンタム・ホース) 編集/小池真幸(同) 撮影/岡島たくみ(同)