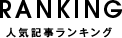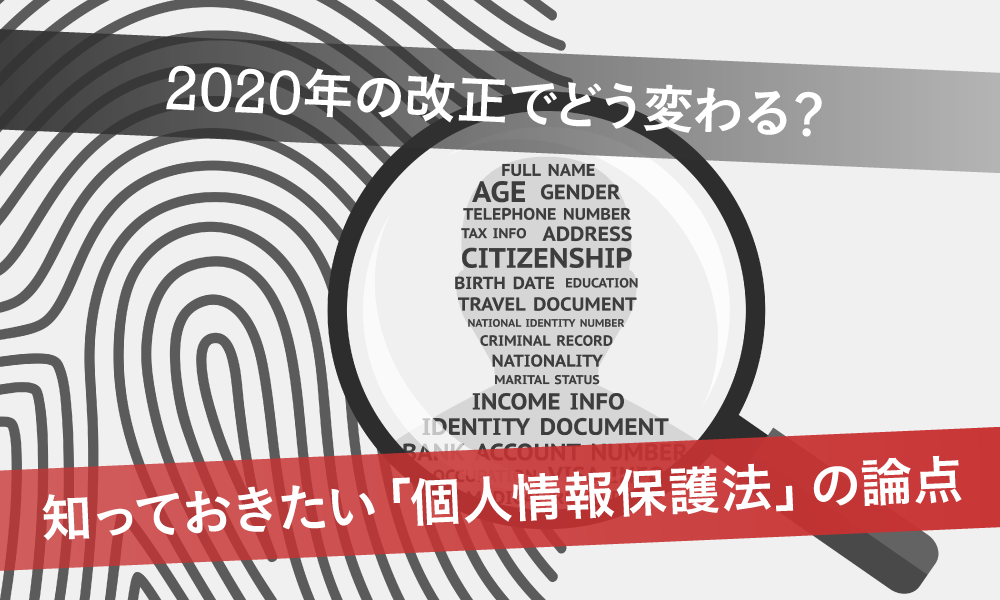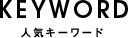次世代移動通信規格5Gの登場を控えて、3DCGでリアルなコミュニケーションができるVR(Virtual Reality)やAR、MRなどのテクノロジーが話題になっている。そうしたなかで、こうしたトレンドの意義を歴史的に知ってほしいと訴える書籍『VR原論』が出版され注目を浴びている。ジャーナリストとして、この分野を長く追いかけてきた著者の服部桂氏は、この「原論」というタイトルにどんな思いを込めたのか?
30年前に、すでにVRはあった!
ここ数年、「VR元年」という言葉がよく聞かれ、私たちの生活にも身近なテクノロジーになりつつある。
製品としては、Facebookがスタンドアローン型VR用HMD(Head Mounted Display)の「Oculus Quest」を5月に発売し、Microsoftは現実空間と仮想空間を融合させた複合現実であるMR(Mixed Reality)の「HoloLens2」を年内に発売する。AR(Augmented Reality)と呼ばれる拡張現実を利用したゲームとしては、ナイアンティックが2012年にベータ版がスタートした「Ingress」、これをベースにした「ポケモン GO」が2016年に登場し、未だに勢いが衰えないことは承知のとおり。発売から3年が経過したPlayStation 4で手軽にVR体験ができる「PlayStation VR」では、今年6月には「みんなのGOLF VR」という話題作が登場し、裾野が広がりつつある。
こうしたなかで、今年は実はVRが商用化されて30年目であることを気づかせてくれる本が出た。朝日新聞で記者や編集者を皮切りに、MITメディアラボ客員研究員などを務め、同社退職後は、関西大学客員教授となり、早稲田大学や女子美術大学などでも教鞭を取る服部桂氏の著書『VR原論』(翔泳社、2019)である。
この本は、1991年に『人工現実感の世界』(工業調査会)というタイトルで出版されたものを大幅加筆して再販したもの。
「『人工現実感の世界』の版元がなくなり、過去のVRのトレンドが忘れられたまま同じような論議が繰り返されているのを見て、正直歯がゆい思いをしていたので、昔の本をどうにか復活させようと奔走しました。いま、VRブームと言われていますが、テクノロジーばかりか精神的なものも含め、誕生した頃の歴史から学べることは多いと思うので」と著書の服部氏は、新聞や雑誌などを通してインターネットが盛んになる以前からVRが誕生した頃の興奮をリアルタイムで伝えてきたゆえに、いまの“盛り上がり”を複雑な気分で受け止めているようだ。

MITメディアラボで受けた衝撃
服部氏は早稲田大学の理工学部を卒業し、1978年に朝日新聞に入社する。当時は、米ソの対立する冷戦の時代で、コンピューターは大型電子計算機と呼ばれ、主に大企業の業務に使われていた。パソコンは出たばかりでまだオモチャ扱いで、インベーダーゲームが流行り、ウォークマンが登場した頃でもある。そして、朝日新聞では、次の時代の新聞のあり方を研究する部署に所属し、80年代のニューメディアブームのど真ん中で仕事をする。
「当時は、“情報”はコンピューターを、“通信”は電話を意味していましたが、両者がつながった分野を“情報通信”と呼ぶようになり、一般向けにそれをニューメディアと言っていました。この分野を新聞社が注目をしたのは、近い将来は、新聞は紙に刷ったものを宅配するのではなく、通信で各家庭に届けられ、ファックスやテレビなどで表示するようになると言われていたためです。このほか通信衛星で放送する、NTTに対抗して電話サービスを始めるなど、いろいろな動きがありました。私はこうした将来のビジネスを扱うニューメディア本部という部署に配属になり、NTTに対抗して世界最大の電話会社AT&Tとオールジャパンが組む次世代の通信インフラを構築する会社に出向することになりました」
今では想像できないが、当時は一般の人々が使う公衆電話回線網に電話機以外の機器、例えばコンピューターをつなぐことは基本的に禁止されていたのだが、法改正によりファックス(ファクシミリ)がつなげるようになってから状況が少しずつ変わり、その後、コンピューターをつないでやり取りをするパソコン通信と呼ばれるサービスが普及していく。 日本でつくば万博(茨城県)が開催された1985年に、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)の建築・計画スクール内にMITメディアラボと呼ばれる研究所が設立され、服部氏は87年からこの研究所の客員研究員となった。
「(ニコラス・)ネグロポンテという建築学科の有名な先生が、21世紀にはコンピューターがテレビや新聞に代わる新しいメディアになると主張して、大きな画面が生活で身近になり、そこに新聞が表示されて、動画が動いていてというような、デモしていたんです。未来を言葉で想像するだけではなく、実際に体験してもらって具体的な論議を進めようとする新しいスタイルが世界中で話題になり注目を集めていました。
そこではすでにVRの研究をやっていて、将来のコンピューターはこういう使われ方をするのかと驚きました。当時のコンピューターは文字しか扱えず行ごとにコマンドを打つような使い方しかできず、やっと表計算ソフトが出てきたころでした。ワープロは専用機が主流で、ようやくDTPが出たばかりのレベル。画像や動画は扱えないし、音なんて、付け足しという感覚でした。

日本に帰ってきたら、当時の通産省(現・経済産業省)がアメリカの最先端コンピューターの展示会を東京・外苑前のTEPIA(高度技術社会推進協会)という施設で行なっているというので見に行くと、VPL リサーチ社のデータグローブと、データスーツ(センサー付きのボディスーツ)を展示していたんです。これが89年6月に米国で発売された、最初の商用のVR製品なんです。そこで最初のVRの本を書きましたが、今回はこの製品の発売された年をVR元年と位置づけ、それを知っていただきたいと思ってあえて『原論』と銘打って再度出したんです」
服部氏は、ケヴィン・ケリーの著書『<インターネット>の次に来るもの』の翻訳者として活動するほか、メディア学者として有名なマーシャル・マクルーハンの入門書を著すなど、テクノロジーの変遷や、その進化については昔から関心を寄せてきた。
「マクルーハン的にいうならば、人間は、身体的限界によって制約されていた欲求の壁を超えるために、テクノロジーを発展させてきた歴史があります。それは言葉から始まり、石器、そして農耕器具や水車、さらには産業革命期の蒸気機関と発展する。その後、そうしたテクノロジーが情報で動いていること理解されるようになり、それがコンピューターによって拡張されていき、最終的には人間そのものを機械で作ればいいのではないかという考えに行き着きます。
しかし、そこで超えられないのは人間の有限性です。いくら身体的限界を技術によって拡張しようとしても、人間は必ず死ぬ存在です。AIやシンギュラリティの議論を観察していると、その人間の有限性を念頭におかず、テクノロジーによって無限に進化するという幻想に取り憑かれているような印象を持つこともあります。コンピューターは、本質的には死についてはわかりませんから、人間と同等の存在にはなりえないのです。したがって、コンピューターが人間を超えるというシンギュラリティのような論議をすることは、あまり意味がないのではないかと思います。
ケヴィン・ケリーと話をしていると、彼は、より本質的な視点で物事を捉えていて、宇宙の始原から考えれば、いま起こっている様々な現象は、サブカテゴリーに属するもので、本質的ではないということを言おうとしているように思います。国家間の紛争も当事者同士では解決が付きませんが、宇宙や世界という上のレベルから見ればサブ問題として理解することができます。目の前の問題にばかりとらわれずに、より根源的な現象の奥にある基本的な原理は何か、ということに注目しないといけないと主張しているのだと思います。どんなにテクノロジーが進化しても人間自体はそれほど変わらないので、テクノロジーの変化をやみくもに追いかけるより、それを生み出している人間に注目したほうが本質的で普遍的な論議ができるのではないでしょうか」
服部氏は、産業革命によってテクノロジーが力を持ち、神に頼らずとも理想的な社会が築けるとした、電話や映画などが発明された19世紀末のメディア革命が起きた時代と同じような現象が、いまネット社会でも起きていると考える。VRやAIなどの個別のテクノロジーの利便性ばかりを論議するのではなく、テクノロジーが人間とどう関わり人間性を変えていったかを学ぶことで、これからの情報社会の姿をより正確に理解し展望できるのではないかと、ニューメディア時代のメディアの歴史を扱う本を執筆中だ。

服部 桂 氏
1951年生まれ。早稲田大学理工学部修士。1978年に朝日新聞に入社。80年代の通信自由化の際、米AT&Tと日本企業の通信ベンチャー企業に出向。87年から2年間、米MITメディアラボ客員研究員。科学記者、「ASAHIパソコン」副編集長、「PASO」編集長など経て、その後は、デジタル面、「be」を担当。2011年からジャーナリスト学校でメディア研究誌「Journalism」を編集。著書に『マクルーハンはメッセージ』(イースト・プレス、2018)など。訳書にケヴィン・ケリー著『テクニウム テクノロジーはどこへ向かうのか?』(みすず書房、2014)、『<インターネット>の次に来るもの』(NHK出版、2016)などがある。